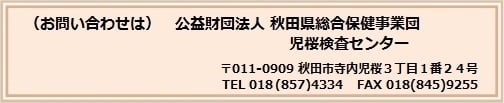臨床検査案内
臨床検査部門は現在大きくふたつの事業を展開しています。
①登録衛生検査所(臨床検査センター)として県内の各病・医院から血液や尿といった検体を預かり検査結果を報告しています。
②検診団体の検査部門として特定健診や職域健診といった検診の際の血液や尿を検査して検診部門へフィードバックしています。
検査を実施していく際に求められるのが検査の正確性ですが内部での精度管理はもちろんのこと、外部精度管理(日本医師会、日本臨床衛生検査技師会などが主催する精度管理調査)にも積極的に参加しています。
実際の検査部門を簡単にご紹介します。
■生化学検査

肝機能検査(AST,ALT,GGT)や血中脂質検査(T-CH,HDL-CH,TG)、血糖検査など健康診断でもよく耳にする項目も含め、多くの項目を大型の分析装置を使用して分析しています。
■免疫血清検査
■一般臨床検査
■微生物検査

口腔粘液や喀痰、尿や糞便、膿(うみ)や血液の中に細菌がいないか、もしいたらどのような種類の細菌がいるのかを調べます。また検出された細菌にどのような薬剤が有効なのかも調べます。
また最近、感染者が増加の傾向にあるといわれている結核についても、結核菌の検査を実施しています。結核菌は増殖する早さがゆるやかなため最終的に結核菌と判断されるまで6~8週間かかりますが、最近では新しい検査法が用いられて2~3日でわかるようになりました。
■病理組織検査

手術の際に摘出した臓器や、胃内視鏡検査等の際に採取した米粒ほどの大きさの組織から標本を作製して、悪性(ガン)や炎症などがないかを診断します。
■細胞診検査
喀痰(かくたん)や尿、婦人科のスメアなどの中の細胞に、悪性細胞(がん細胞)がないかどうかを顕微鏡で観て診断します。検診の際に採取された喀痰や婦人科のスメアは、肺ガンや子宮ガンの早期発見に役立っています。
検査案内冊子
検査案内2022.pdf (2022-06-01 ・ 3889KB) 令和4年度の検査案内冊子です。 |